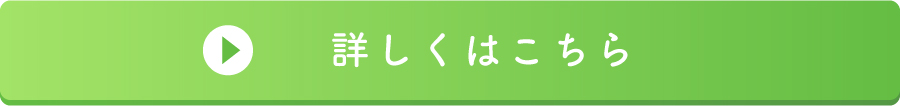氷食症かも?疲れやすさと氷への渇望が示す体からの重要なSOS 🧊
掲載日:2025.08.12(最終更新日:2025.08.12)

「なんだか最近、氷をガリガリ食べるのがやめられない…」
「製氷皿1皿分くらい毎日食べてしまう」
そんな経験はありませんか?🤔
単なる癖だと思っていたその行動、実は体からの重要なSOSサインかもしれません。
今回は、氷への異常な渇望と疲れやすさの関係について、詳しく解説します。
▶️ 動画で見たい人はコチラ:「氷を毎日食べたくなる人は要注意!疲れやすい 頭痛 イライラ 腰痛 氷食症 かも?」
1.氷食症とは何か?基本的な症状をチェック
2.疲れやすさと氷への渇望の正体 🔍
3.こんな症状があったら要注意!セルフチェック項目 ⚠️
4.放置すると危険!氷食症が与える深刻な影響 😰
5.正確な診断のための検査方法 🩺
6.効果的な治療法と改善方法 💊
7.食事による改善法 🍽️
8.サプリメント選びのポイント 💊
9.予防と日常生活での注意点 🌟
10.体のSOSサインを見逃さないために 📝
11.よくある質問Q&A 🤔
1.氷食症とは何か?基本的な症状をチェック ✅

氷食症は医学的に「pagophagia」と呼ばれ、異食症の一種です。
この症状の特徴として、1日に製氷皿1皿分以上の氷を食べる、氷を口の中で溶かすのではなく「ガリガリ」と噛み砕いて食べる、氷を食べないとイライラや不安を感じる、季節に関係なく年中氷を求める、他人のグラスの氷まで食べてしまうなどの行動が見られます。
氷食症チェックリスト
✅1日に製氷皿1皿分以上の氷を食べる
✅氷を口の中で溶かすのではなく「ガリガリ」と噛み砕いて食べる
✅氷を食べないとイライラや不安を感じる
✅季節に関係なく年中氷を求める
✅他人のグラスの氷まで食べてしまう
どんな人に多いの?
氷食症は圧倒的に女性に多く見られる症状です。特に、
・20代〜40代の女性👩
・思春期の女性
・妊娠中・授乳中の女性🤱
に頻繁に発症します。統計によると、鉄欠乏性貧血患者の約16%に氷食症が認められており [1]、興味深いことに、男性でも鉄欠乏性貧血患者の34%に氷食症が見られることが報告されています[2]。
2.疲れやすさと氷への渇望の正体 🔍

⚠️氷食症の背景には、多くの場合「鉄欠乏性貧血」が隠れています。
しかし、ここで注意したいのが「隠れ貧血」の存在です。
隠れ貧血とは、ヘモグロビン値は正常範囲内にあるものの、体内の鉄の貯蔵量(フェリチン値)が不足している状態を指します。
この段階でも氷食症などの症状が現れることがあるため、一般的な健康診断で「貧血ではない」と言われても、実は鉄不足が進行している可能性があるのです。
3.こんな症状があったら要注意!セルフチェック項目 ⚠️
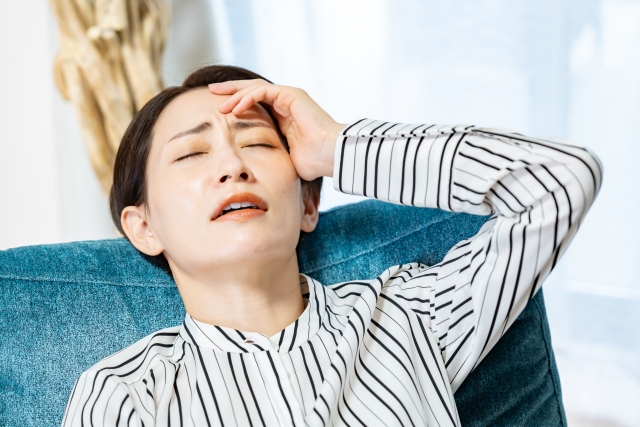
氷食症と合わせて以下の症状がある場合は、隠れ貧血の可能性が高くなります:
体の症状
✅疲れやすい、だるさが続く
✅息切れや動悸がする
✅めまいや立ちくらみがある
✅朝起きるのがつらい
✅集中力が低下している
見た目の変化
✅爪が薄くなった、割れやすい
✅髪が抜けやすくなった
✅肌が青白く見える
✅口角が切れやすい
精神的な症状
✅イライラしやすい
✅抑うつ症状がある
✅記憶力が低下した気がする
これらの症状が複数当てはまる方は、早めに医療機関での検査をおすすめします。
4.放置すると危険!氷食症が与える深刻な影響 😰

氷食症を放置すると、まず歯への深刻な損傷が起こります。
硬い氷を毎日大量に噛み砕くことで、エナメル質の摩耗による知覚過敏が発生し、歯の欠けや最悪の場合は抜歯が必要となることもあります。また、顎に大きな負担がかかることで顎関節症のリスクも増加します。
より深刻なのは、根本原因である鉄欠乏性貧血の悪化による全身への影響です。疲労感や息切れの増悪、免疫力の低下、血行不良による内臓機能低下が進行します。女性の場合には、月経不順や不妊の原因となることもあるため、特に注意が必要です。
5.正確な診断のための検査方法 🩺
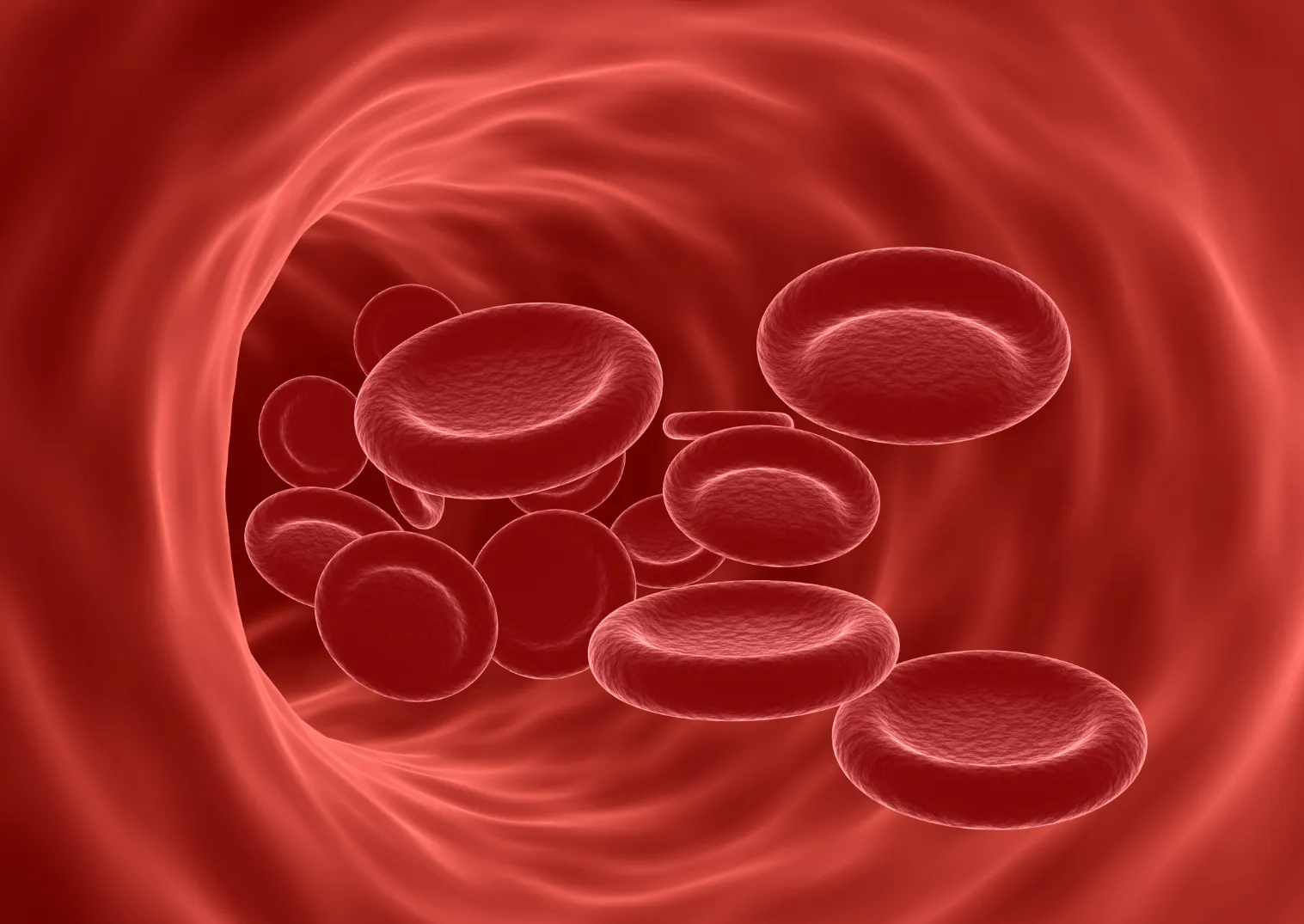
重要な血液検査項目
氷食症の診断で最も重要なのは血液検査です。
必須となる検査項目には、一般的な貧血指標であるヘモグロビン値、血液中の鉄濃度を示す血清鉄、そして最も重要な体内の鉄貯蔵量を表すフェリチン値があります。
診断基準として、フェリチン値が12ng/mL以下の場合に鉄欠乏性貧血と診断されます[4]。ただし、一般的な健康診断では測定されないことが多いため、氷食症を疑う場合は必ず医師にフェリチン値の測定を相談することが大切です。
なぜフェリチン値が重要なのか?
フェリチン値は体内の鉄の貯蔵量を示す指標で、隠れ貧血の発見に欠かせない検査です。ヘモグロビン値が正常でも、フェリチン値が低下していれば鉄欠乏症と診断されるため、氷食症の根本原因を見つけるためには必須の検査項目となります。
6.効果的な治療法と改善方法 💊

氷食症の治療において第一選択となるのは鉄剤の内服治療です。
治療開始後、数日〜数週間で氷への渇望が軽減されることが多く[5][6]、通常2〜6ヶ月程度の治療期間が必要となります。
7.食事による改善法 🍽️

ヘム鉄を多く含む食材(吸収率が高い)
鉄分には吸収率の高いヘム鉄と、吸収率の低い非ヘム鉄があります。ヘム鉄を多く含む食材には、レバー(鶏・豚・牛)、赤身の肉(牛肉、豚肉)、カツオやマグロなどの赤身魚、あさりやしじみなどの貝類があります。
非ヘム鉄を多く含む食材
植物性食品に含まれる非ヘム鉄は、ほうれん草や小松菜などの葉物野菜、ひじきやわかめなどの海藻類、納豆や豆腐などの大豆製品、レーズンやプルーンなどのドライフルーツに豊富に含まれています。
吸収率を高める工夫 ✨
非ヘム鉄の吸収率を高めるためには、ビタミンCと一緒に摂取することが効果的です。レモン、ピーマン、ブロッコリーなどのビタミンC豊富な食材を組み合わせましょう。具体的な例として、ほうれん草のおひたしにレモンを絞ったり、ひじきの煮物にピーマンを加えたりする工夫があります。
吸収を妨げる食品に注意 ⚠️
一方で、鉄の吸収を阻害する食品もあります。コーヒー、紅茶、緑茶に含まれるタンニン、牛乳などの乳製品に含まれるカルシウム、玄米や全粒粉に含まれるフィチン酸は鉄の吸収を妨げるため、鉄分豊富な食事との時間をずらして摂取することをおすすめします。
8.サプリメント選びのポイント 💊

サプリメントを選ぶ際のポイントとして、吸収率が高く胃腸負担が少ないヘム鉄を使用したもの、ビタミンCや葉酸が配合されているもの、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが大切です。
ただし注意点として、鉄分の過剰摂取は体に害を与える可能性があるため、必ず用量を守って服用し、医師との相談を行うことが推奨されます。
9.予防と日常生活での注意点 🌟

氷食症の予防は、日常生活での工夫が重要です。食事面では、バランスの良い食事を心がけ、鉄分を意識した献立作りを行い、ビタミンCを積極的に摂取することが大切です。
生活習慣の改善として、規則正しい生活リズムを保ち、適度な運動で血行を促進し、ストレス管理を行うことも予防に効果的です。
定期検査の重要性として、年1回の健康診断でヘモグロビン値をチェックし、必要に応じてフェリチン値測定を依頼することをおすすめします。特に女性の場合は、月経の状態も記録しておくことが有用です。
10. 体のSOSサインを見逃さないために 📝
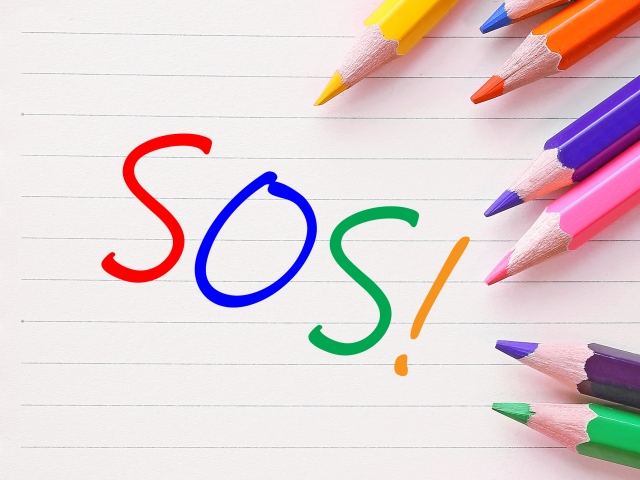
氷への異常な渇望と疲れやすさは、決して軽視してはいけない体からの重要なSOSサインです。
1日に製氷皿1皿分以上の氷を食べるのは異常な状態であり、隠れ貧血の可能性を考慮した血液検査が必要です。特にフェリチン値の測定が診断の鍵となり、適切な治療により改善が期待できるため、早期発見・早期治療が重要となります。
もし思い当たる症状がある方は、「単なる癖」と軽く考えず、ぜひ一度医療機関を受診してください。適切な診断と治療により、氷食症は改善できる症状です。
あなたの健康を守るために、体が発するサインに敏感になり、必要な時は迷わず専門医に相談することが大切です。
当院では、自費の詳細な血液検査、栄養解析を実施しています。
11. よくある質問 Q&A🤔

Q: 氷食症は遺伝しますか?
A: 氷食症自体は遺伝しませんが、鉄欠乏になりやすい体質は遺伝的要因もあります。
Q: 男性でも氷食症になりますか?
A: はい。男性でも鉄欠乏性貧血患者の34%に氷食症が見られます[2]。
Q: 子どもの氷食症はありますか?
A: あります。特に思春期の女性に多く見られ、成長期の鉄需要増加が関係しています。
Q: 氷食症は完治しますか?
A: 根本的な鉄欠乏を改善すれば、多くの場合症状は自然に消失します。
【引用文献】
- Uchida T, Kawati Y. Pagophagia in iron deficiency anemia. Rinsho Ketsueki. 2014 Apr;55(4):436-9.
- Barton JC, Barton JC, Bertoli LF. Pagophagia in men with iron-deficiency anemia. Blood Cells Mol Dis. 2019 Jul;77:72-75.
- Hunt MG, Belfer S, Atuahene B. Pagophagia improves neuropsychological processing speed in iron-deficiency anemia. Med Hypotheses. 2014 Oct;83(4):473-6.
- Uchida T, Kawati Y. Pagophagia in iron deficiency anemia. Rinsho Ketsueki. 2014 Apr;55(4):436-9.
- Osman YM, Wali YA, Osman OM. Craving for ice and iron-deficiency anemia: a case series from Oman. Pediatr Hematol Oncol. 2005 Mar;22(2):127-31.
- Rabel A, Leitman SF, Miller JL. Ask about ice, then consider iron. J Am Assoc Nurse Pract. 2016 Feb;28(2):116-20.